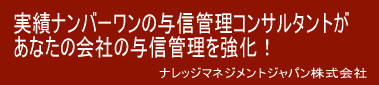| ---------------------------------------------------------------------- |
| 与信管理入門 第17回 営業活動によるキャッシュフローと間接法 |
| ---------------------------------------------------------------------- |
キャッシュフロー計算書の作成には、直接法と間接法があるが、ほとんどの企業は、間接法で作成している。
直接法の作成は、収入と支出を総額で表示するのだが、非常に手間がかかるためである。
どちらの手法を用いても、見た目は異なるが結果は同じになる。
また、投資活動によるキャッシュフローと財務活動によるキャッシュフローは見た目も同じである。営業活動によるキャッシュフローのみ見た目が大きく異なる。
間接法の場合、税引き前の当期純利益から始まり、実際のキャッシュの出入りに伴い、調整を行っていく。
代表的な科目が「減価償却費」である。建物や機械、車両などの固定資産は、時間の経過と共にその価値が低下していく。こうした資産を減価償却資産という。
こうした減価償却資産の取得費用を使用年数に応じて配分して、費用化とすることを減価償却という。
有形固定資産の中でも、土地は価値が時間の経過で価値が劣化しないと考えられており、減価償却の対象ではない。
一方、無形固定資産の中にも、ソフトウェアなど減価償却の対象となっている資産もある。
実際、固定資産を購入した時点でキャッシュは企業から出て行っているが、その購入金額を一括で費用計上することができない。
税制で定めた法定耐用年数に従い、一定の割合や金額を毎年、費用計上していくのだ。
この減価償却費は、P/Lの販売及び一般管理費に計上される。つまり、その分だけ利益を押し下げる要因となっている。
しかし、実際、キャッシュは出て行っていないために、営業活動によるキャッシュフローにおいては、減価償却費を足し戻すことになる。
キャッシュフロー計算書を作成していない中小企業の営業活動におるキャッシュフローを推測するのに、税引き前当期純利益に減価償却を加えて代用することがある。
ナレッジマネジメントジャパン株式会社
代表取締役 / 与信管理コンサルタント
牧野和彦
|
| ---------------------------------------------------------------------- |